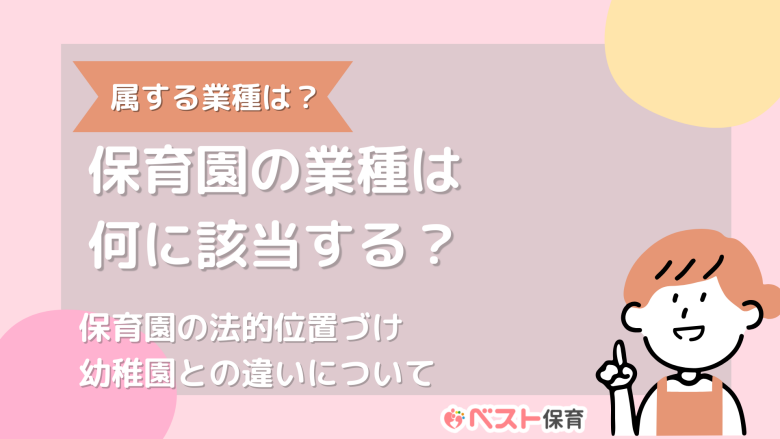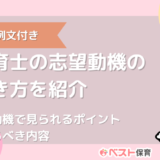保育士として働く際、公的書類や転職活動で「業種」や「職種」を記載する必要がある場面があります。
しかし、「保育園や保育士はどの業種に該当するのか?」や、「職種として何を記載すべきか」といった点で悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、保育園や保育士が該当する業種・職種の正しい記載方法について解説します。
また、保育士資格を活かした転職先や、保育園と幼稚園の法的位置づけの違いについても詳しく紹介します。
- 保育園の業種は「児童福祉事業」に該当
- 保育園の法的位置
- 社会福祉法人の保育園と株式会社の保育園との違い
- 保育園と幼稚園の違い
目次
保育園の業種は「児童福祉事業」に該当
保育園の業種は、日本標準産業分類において「児童福祉事業※」に該当します。
これは、大分類である「医療・福祉」に含まれ、中分類の「社会保険・社会福祉・介護事業」の一部として位置付けられるものです。
さらに具体的には、小分類の「児童福祉事業」に分類され、子どもたちの健全な成長を支える社会的な役割を担っています。
参照:総務省|日本標準産業分類より
保育園は、厚生労働省が管轄する福祉施設であり、社会福祉事業の一環として運営されています。
このため、公的書類などで業種を記載する際には、「医療・福祉業」や「社会福祉」と記載するのが一般的です。
また、選択肢の中に適切な項目が見つからない場合でも、「その他」を選ぶことで問題ありません。
また保育士は、看護師や介護士と同じ「医療・福祉」大分類に属しますが、児童を対象とした福祉活動に特化した職種です。
この点が、他の福祉職種との大きな違いであり、「児童福祉事業」という名称からも、子どもに特化した支援業務であることが明確にわかります。
業種を正確に記載することで、保育園や保育士が担う重要な役割を正しく伝えましょう。
保育園の法的位置
保育園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号※)に基づいて設置される児童福祉施設であり、厚生労働省の管轄下にあります。
参照:|児童福祉法より
この法的な位置づけにより、保育園は保育を必要とする乳児や幼児に対して、心身の健全な発達を促進するための福祉的な支援を行う場として設立されています。
- 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。
- 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。
- 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。
- 保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものであり、その職責を遂行するための専門性の向上に絶えず努めなければならない。
参照:厚生労働省告示第百十七号|保育所保育指針_保育所保育に関する基本原則_保育所の役割より
保育所が認可を受けるためには、児童福祉施設の設備や運営に関する基準を満たす必要があり、これらの基準は保育の質を確保するために設けられています。
保育園は、単に子どもを預かる場所ではなく、専門的な知識を持った保育士が養護と教育を一体的に提供する施設です。
保護者との密接な連携をもとに、子どもの発達段階や個別の状況に応じた支援を行い、地域の子育て支援にも寄与しています。
.png) 保育士
保育士
また、保育所は社会的責任を持ち、入所する子どもの福祉を積極的に増進する役割を担っています。
そのため、保育園は家庭や地域社会と連携を取りながら、子どもの発育を支援する重要な社会資源と位置づけられています。
社会福祉法人の保育園と株式会社の保育園との違い
社会福祉法人の保育園と株式会社が運営する保育園には、運営方針や資金調達方法に大きな違いがあります。
ここでは、運営母体、運営費用、給料の3つの観点から違いを解説します。
運営母体の違い
社会福祉法人と株式会社では、運営母体に大きな違いがあります。
例えば、社会福祉法人の保育園は、社会福祉事業を目的に設立された非営利法人で、保育園をはじめ、医療や介護などの福祉事業を行います。
法人の運営は自治体の監督下で行われ、主に補助金や寄付金が運営資金の大部分を占めています。
一方、株式会社の保育園は営利法人で、保育園の運営には株式や営業による利益が利用されます。
株式会社は利益を追求するため、事業の展開が柔軟であり、経営者の理念やアイデアに基づいて運営されています。
運営費用の違い
運営費用に関しても、社会福祉法人と株式会社では異なります。
社会福祉法人は非営利のため、国や地方自治体からの補助金が支給されることが多く、税制上の優遇措置を受けて施設を運営していきます。
このため、運営資金が安定しており、経営面での負担が少ないという特徴があります。
対照的に、株式会社は営利法人であるため、税制上の優遇措置はなく、運営資金は主に事業活動から得た利益に依存します。
株式会社が運営する保育園は、市場のニーズに応じた運営が求められるため、柔軟で迅速な対応が可能ですが、安定した補助金が少ない点が課題となります。
給料額の違い
給料額に関しては、社会福祉法人と株式会社の運営する保育園で差が見られます。
厚生労働省の調査※によると、社会福祉法人の保育園では保育士の平均月給が約25万円に対し、株式会社が運営する保育園では約22万円となっています。
| 運営元 | 社会福祉法人 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 保育士 | 月額約25.8万円 ※平均勤続年数10.4年 |
月額約22.7万円 ※平均勤続年数4.1年 |
| 施設長 | 月額約54.7万円 ※平均勤続年数25.3年 |
月額約34.6万円 ※平均勤続年数10.4年 |
参照:厚労省|幼稚園・保育所等の経営実態調査結果( 収 支 状 況 等 )より
この差は、主に運営資金の安定性に起因します。
社会福祉法人は補助金を受けるため、安定した運営が可能であり、その分、給与の水準が高めになる傾向があります。
一方、株式会社は営利目的で運営されるため、給料が低めに設定されることがありますが、給与改善に向けた取り組みを行っている企業も増えており、今後の改善が期待されています。
保育園と幼稚園の違い
保育園と幼稚園は、どちらも幼児を対象にした施設ですが、その制度や運営目的、設置基準には大きな違いがあります。
それぞれの違いを6つの観点から詳しく解説します。
| 施設 | 保育園 | 幼稚園 |
|---|---|---|
| 適用される法律・所管 | 「児童福祉法」(厚生労働省) | 「学校教育法」(文部科学省所管) |
| 施設の目的 | 保護者の委託を受けて、乳児または幼児の保育 | 幼児を保育し、適切な環境下で心身発達の助長 |
| 保育対象 | 保育にかける乳児(1歳未満)~幼児(1歳~小学校就学始期に達するまでの幼児) | 満3歳~小学校就学始期に達するまでの幼児 |
| 設置者 | ・公立:市町村 ・私立:社会福祉法人等 ※設置には知事の許可が必要 |
・公立:市町村 ・私立:学校法人等 ※設置には市町村立幼稚園の場合は都道府県教育委員会、私立幼稚園の場合は知事の許可が必要 |
| 設置・運営の基準 | 児童福祉施設最低基準 | 幼稚園設置基準 |
| 1日の教育・保育時間 | 約8時間 | 約4時間 |
管轄の違い
保育園は厚生労働省の所管であり、児童福祉法に基づく児童福祉施設です。
一方、幼稚園は文部科学省の所管で、学校教育法に基づく学校教育施設として運営されています。
この違いは、施設の運営方針や役割に直結します。
例えば、保育園は福祉的な観点から、保護者が保育に欠ける状況での支援を目的としています。
一方、幼稚園は教育施設として幼児期の心身の発達を助長する役割を担っています。
管轄する省庁が異なるため、行政手続きや基準の適用にも違いが生じます。
施設目的の違い
保育園の目的は、保護者の委託を受けて保育に欠ける乳幼児を日々保育することにあります。
このため、長時間保育が可能で、基準として8時間の保育支援を提供することが一般的です。
一方、幼稚園の目的は、幼児に適切な教育環境を提供し、心身の発達を促すことです。
保育時間は4時間が基準となっており、教育に重点を置いたカリキュラムが実施されています。
保育園と幼稚園は、対象となる子どもや運営の背景に応じて異なるサービスを提供している点が特徴です。
設置者の違い
保育園と幼稚園は設置主体も異なります。
| 施設 | 運営元 | 設置許可 |
|---|---|---|
| 保育園 | ・公立施設:市町村 ・私立施設:社会福祉法人 |
都道府県知事の許可が必要 |
| 幼稚園 | ・公立施設:市町村 ・私立施設:学校法人 |
・市町村立:都道府県教育委員会 ・私立:都道府県知事の許可 |
これらの違いにより、施設の運営方針や管理基準も変わるため、選ぶ際には設置者や施設の目的を確認することが重要です。
保育対象者の違い
幼稚園と保育園の主な違いの一つは、保育対象者です。
幼稚園は満3歳から小学校就学前の幼児を対象としており、主に教育を目的としています。
これに対して、保育園は0歳児から小学校就学前の子どもを対象にしており、保護者の就労などにより保育に欠ける子どもを受け入れます。
保育園は幅広い年齢層の子どもを受け入れるため、特に乳幼児や早期の段階から保育を提供しています。
教育・保育内容の基準の違い
教育と保育の内容においても、幼稚園と保育園には大きな違いがあります。
幼稚園は「幼稚園教育要領」に基づき、幼児の心身の発達を促す教育が行われます。
教育の主な焦点は、幼児の自発的な活動や遊びを通して心身の調和の取れた発達を促すことです。
対して、保育園は「保育所保育指針」に基づき、保育に欠ける子どもたちの養護と教育を一体的に行い、家庭との連携を重視して福祉的支援が提供されます。
保育所では子どもが自発的に活動できる環境作りや、社会的な力を育む場作りが強調されます。
運営費負担の違い
運営費の負担にも違いがあります。
幼稚園は主に保護者が授業料を支払いますが、近年は無償化政策によってその負担が軽減されています。
これに対して、保育園は国や自治体からの補助金が多く、保護者の負担額は家庭の収入に応じて異なります。
保育園は福祉施設としての性格を持つため、福祉的支援が強調され、保育を必要とする家庭に対する支援の側面が大きいです。
このように、運営費負担の違いは、それぞれの施設の目的や機能に起因しています。
保育園の業種は「児童福祉事業」に属し公的記載では注意しよう
保育園の業種は、法律上「児童福祉事業」に分類され、子どもの福祉を最優先にした事業活動を行っています。
この業種は、児童福祉法に基づき、保育士やその他の職員が子どもたちの健全な成長を支えるために専門的な支援を行うことを目的としています。
保育園が提供するサービスは、子どもたちにとって安全で健康的な育成環境を提供することを中心に、日々の保育業務や学習支援が行われています。
また、保育士やその他の職員は、子どもたちの個性や発達に応じたきめ細やかなケアを提供するため、高い専門性が求められます。
保育園はこの「児童福祉事業」としての役割を果たし、各自治体や施設が定めた規定に従って運営されています。
特に公的な記載を行う際には、この児童福祉事業としての位置づけを明確にする必要があり、行政や関係機関に対する報告義務が生じます。
したがって、保育園の運営や管理においては、法的な要件や規制を遵守することが不可欠です。
この点に注意しながら、保育業界での求人情報や職務内容を理解することが大切です。